
2024年、寒河江市屋内型児童遊戯施設『CLAAPIN SAGAE(クラッピンサガエ)』のオープンに伴い、その運営業務を担当する株式会社ヤマコーに入社した美術科総合美術コース出身の髙野奈美(たかの?なみ)さん。現在は施設内の工作室『てづくりせかい』で、アートエデュケーターとして工作コンテンツの企画や運営、指導などを担当しています。高校と大学を合わせて7年間、美術教育を受けてきた髙野さんだからこそ日々仕事の中で思いを馳せていること、そして子どもたちに伝えていきたいアートの力についてお伺いしました。
? ? ?
一人一人の自主性と意思を尊重
――はじめに『CLAAPIN SAGAE』について教えてください
髙野:“アソビ”と“マナビ”をテーマにした屋内型児童遊戯施設になります。施設内には“未知なるせかいを体験しよう”というコンセプトのもと7つの部屋があり、私が管理を担当する工作の部屋には『てづくりせかい』と名前が付けられています。『てづくりせかい』では工作コンテンツを月ごとに変えているので、その内容を考えたり、お手本を用意したり、つくり方が分からず悩んでいる子どもがいたら教えてあげたり。また小学生を対象にした工作のカルチャー教室の開講や、約月1回ペースでの工作ワークショップの企画?開催なども主な業務になります。

――今までどういった工作コンテンツを企画してきましたか?
髙野:例えばトイレットペーパーの芯が飛び出すおもちゃとか、あとはハロウィンに合わせてステンドグラス風のカードをつくるワークショップとか。ハロウィンらしく「スタッフに合言葉を言うとつくれるよ」というシステムにしたら、結構いろんな子が真剣に楽しんでくれました。
企画を考える時はいつも参考のために図書館に行って本を読んだりするんですけど、施設の利用者の多くは幼稚園から小学校3~4年生ぐらいまでの子どもたちなので、本に載っているものを丸々採用するのではなく、よりこの施設の層に合う形を考えるようにしています。ただ簡単過ぎるとつまらなくなるので、難易度をどう調整するかが今、一番手探りで考えているところですね。あと本当に煮詰まった時はイオンモールに行って館内のポップとか装飾とかを見ていると、アイデアが浮かんできたりします。


「CLAAPIN SAGAE(クラッピン サガエ)」(山形県寒河江市)は、2024年4月にオープン。室内外設備のほか、キャンプ場も備えている。
――ご自身の企画の中で特に印象に残っているものは?
髙野:トイレットペーパーの芯でつくったロケットを、新聞紙と輪ゴムでつくった発射台から飛ばすおもちゃを企画しました。夏休み期間だったのでちょっと刺激的な面白いものをつくらせてあげたくて。その際、人に当たってしまうとあぶないので外で飛ばすことをルールにしたんですけど、それでも絶対、中で飛ばす子がいるだろうなって思っていたらみんなちゃんとルールを守ってくれて、人に向けて飛ばすようなこともなくてすごく良かったです。
工作のワークショップを準備?企画している時は、毎回「お客さんが誰も来なかったらどうしよう」と不安になるんですけど、そんな時にみんな来てくれて、なおかつ目標の人数を超えた時はやっぱり安心しますね。実際、予算との戦いもあってそこが一番ハードルが高いというか(笑) 少ない予算でも楽しんでもらえるようにスーパーから牛乳パックをいただいたり、リサイクルに回すものを譲っていただいたり。あとは寄付してくださる方がいらっしゃったり、スタッフとかパートさんの家庭から出るものを集めておいてそれを材料に回したりという感じですね。

保護者にも伝えていきたい美術の価値
――お仕事をされる上でいつも大切にしていることはありますか?
髙野:もともと美術系の高校だったので、その後の進路も必然的に美術に関係するところになるんだろうなとは思っていました。私は埼玉県越生町にある高校に通っていたんですけど、1年生の時、隣町で開催されたアートイベントに越生高校美術科として作品展示したことがあって、また2年生の時は出展するお店全部の看板を美術部が描きました。会場はその町の山奥にある廃校で、普段は全然人がいないし、周りの集落からも遠いし、バスも通っていないし。なのにイベント当日になったらたくさん人が来て、普段は誰もいないようなところでも、こういうアートイベントをすると人が集まってくることに面白さを感じました。

でも東京の大学でそういう学びができるところがなくて、高校に届いたいろんな大学のパンフレットを片っ端から見ていた時に芸工大の存在を知りました。最初はコミュニティデザイン学科が目に入ったんですが、美術系の高校で三年間、絵を描いたり彫刻したりしてきたので制作することも手放したくなくて。それでもう一度パンフレットを読み返していたら、総合美術コースのところにアートディレクションと書いてあるのを見つけたんです。
その後はオープンキャンパスに行ったり、進学フェアの芸工大ブースで相談したりしながら、出願ギリギリまで悩んだ末、総合美術コースへの進学を決めました。結果、制作もできたしアートディレクションについても学ぶことができて、実践はコロナのせいで減ってしまいましたが、総合美術コースに入ってすごく良かったなって思っています。

――大学時代の学びの中で印象に残っていることは?
髙野:コロナでワークショップができなくなってしまった代わりに、鶴岡市にある児童教育施設『SORAI』へ松村泰三(まつむら?たいぞう)※1ゼミの学生みんなでおもちゃを制作して贈りました。実際にそのおもちゃで遊んでいる子どもたちの写真とか動画を見たら、すごく面白そうに遊んでくれていて嬉しかったですね。
また卒業制作では、箱の中に文学作品の世界観を再現して、自由に手に取って開けてもらうことができる立体コラージュ作品を10種類つくりました。今までずっと美術をやってきて、いろんな素材とか技法を広く扱ってきた自分だからこそ、卒業制作は1個の作品ではなくいろんなものをたくさんつくりたくて。近代文学作品って青空文庫を使って手軽に読めるじゃないですか。そういう面で私の中ではハードルが低くて、結構いろいろ読んでましたね。大人はその本の内容をすでに知っていたりするので、私の作品を見て「あ、これはああいうことね」みたいに先に知識が来る反応なんですけど、子どもは本の内容を知らずに箱の中の仕掛けを見て「面白い」とか「きれい」とか言ってくれるので、その純粋な反応が好きでした。

それから、大学時代は市川寛也(いちかわ?ひろや)先生※2の『東妖研(東北妖怪文化研究センター)』という地域寄りのチュートリアルにも参加していました。妖怪をテーマにイベントを企画する中で、地域の巻き込み方みたいなものを培うことができたと感じています。
※1:美術科?総合美術コース教授。造形作家。詳しいプロフィールはこちら。
※2:2019年度まで美術科?総合美術コース専任講師。現在は群馬大学で教鞭を執る。
――これから挑戦してみたいことはありますか?
髙野:「私はどうしてこんなに苦しいのに美術を続けているんだろう?」という時期が卒業制作の頃に割と長くあったんですね。でもいろんな人に自分の作品を見てもらう中で、高校2年生の女の子が私の作品を見て総合美術コースに入ることを決めたという話を聞いて、「私、このためにやっていたのかもしれない。美術は苦しいこともあるけれどやっぱり楽しいし、決して無駄じゃないということを誰かに伝えたかったのかもしれない」って思ったらすごく腑に落ちて。

実は以前、工作室で絵を描いていた女の子にその子のお母さんとお父さんが「絵“なんか”描いていないであっちの跳び箱で遊ぼうよ」と言っているのを聞いてしまったんです。それがとても悲しくて…。確かに生きていく上で美術は必要ないかもしれないけれど、それでも発想力が培われて何かの土台になっていくことが、美術の持つ一番大きな力だと思うんです。なのでカルチャー教室に来ている子どもたちには、「美術って楽しいだけじゃないけど、得られるものも多いんだよ」と伝えるようにしています。
そして、保護者の方にも「美術や工作をしていてマイナスになることはない」と声を大にして言っていきたいですし、工作室への敷居をもっと下げられるような仕組みや仕掛けができたらいいなと思っています。
――最後に受験生へメッセージをお願いします
髙野:もし総合美術コースに惹かれて「入りたい」と思ってくれているなら、入学するまでに自分の好きなこととか得意なこと、やりたいことを明確にしておけるといいかもしれません。いろんなことができるコースだからこそ、自分の軸みたいなものをなんとなくでもいいから見つけておけるといいのかなと。私の場合は最初から「地域で何かしたい」という思いがあったので、その中で東妖研でもお世話になった市川先生についていくことで力を付け、また市川先生の異動後は松村先生のもとで学ばせてもらって。そうやってスタートダッシュが遅れないというのはすごく大事なことですし、同じ四年間でも密度が違ってくると思います。

? ? ?
ハロウィンの工作でヨーヨーづくりを企画した際、お手本としてパンプキンやお化けやガイコツをつくり、またオレンジと白と黒と薄紫の折り紙を出しておいたところ、工作に来ていた女の子が白と黒と薄紫を組み合わせてサンリオキャラクターのクロミちゃんをつくっていたことに驚いたという髙野さん。「お手本があって材料も絞られている中、自分が好きなものを上手くつくれるってすごいですよね。そういう瞬間に立ち会えるのがすごく面白いです」。子どもならではの自由な発想を目の当たりにできる―。その感動をパワーに変え、髙野さんは今日も美術を学ぶ意義とその価値を伝え続けています。
(撮影:渡辺然、取材:渡辺志織、入試課?須貝)
さくらんぼこどもキャンパス CLAAPIN SAGAE クラッピンサガエ Webサイト
さくらんぼこどもキャンパス CLAAPIN SAGAE クラッピンサガエ Instagram
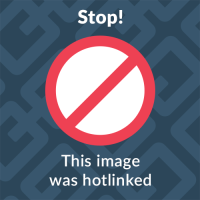
東北芸術工科大学 広報担当
TEL:023-627-2246(内線 2246)
E-mail:public@aga.tuad.ac.jp
RECOMMEND
-
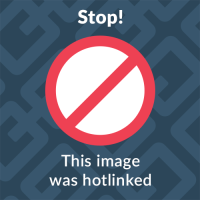
2023.03.03|インタビュー
自分が挑戦してみたい展示の企画を、一から考え作っていける面白さ/花巻市博物館?卒業生 髙橋静歩
#卒業生#歴史遺産 -

2025.04.08|インタビュー
“柔軟なデザイナー”を目指し、理想の製品を追い求める日々/株式会社マーナ?卒業生 菅野彩瑛
#プロダクトデザイン#卒業生 -
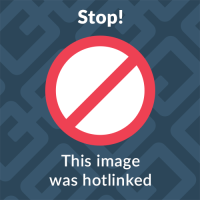
2023.03.13|インタビュー
思考を変換し、柔らかく生きることで増えていく将来への選択肢/就職部長 粟野武文教授
#教職員




