
『崎山貝塚縄文の森ミュージアム(岩手県宮古市)』に併設された埋蔵文化財センターで、文化財調査員として働く宮古市教育委員会事務局文化課所属の上條瑞貴(かみじょう?みずき)さん。普段は主に、出土した埋蔵文化財の保存管理や発掘調査などを行っています。在学中は歴史遺産学科で考古学を専攻。縄文土器をテーマにした卒業論文にも取り組みました。そんな上條さんに、宮古市周辺で発掘される埋蔵文化財の特徴や、大学時代に経験した貴重なフィールドワークの思い出などをお聞きしました。
? ? ?
効率性が求められる緊急発掘の仕事
――はじめに埋蔵文化財センターで働くことになった経緯と、現在のお仕事内容について教えてください
上條:『宮古市崎山貝塚縄文の森ミュージアム』が開館して1年経った頃、一度訪れて観た展示がすごく面白くて印象に残っていました。そしたら試験があると聞いて、受けてみようかなと。もともと就職は民間企業で考えていたんですけど、地元で受けた企業の採用試験に落ちた時、なぜかショックを受けなくて。それどころか自分がやりたいのは行政の方ではないかと気付き、所属していた学科の青野友哉(あおの?ともや)先生※にアドバイスをいただきながら採用試験に挑んだ結果、無事宮古市に合格しました。

現在は埋蔵文化財の保存管理や、市民の皆さんに埋蔵文化財を紹介する公開活用事業などを担当しています。また冬の時期以外は発掘調査事業も行っていて、発掘後の遺物整理や、あとは遺跡が残っているかどうかを現地に行って確認したり、もし遺物が転がっている場合は試掘調査の対応をしたり。それから一眼レフを使って遺物の写真を撮ったりしています。
※歴史遺産学科?歴史遺産コース教授。考古学者。詳しいプロフィールはこちら。
――宮古市周辺で発掘される文化財に特徴はありますか?
上條:この辺りだと大木式土器(だいぎしきどき)※と呼ばれる縄文時代中期のものが結構多いですね。あと崎山貝塚からもう少し南の方に行くと、奈良時代や平安時代といった古代の製鉄の遺跡が多くあります。また、宮古市では基本的に縄文時代晩期の資料はなかなか出ないんですけど、近内中村遺跡(ちかないなかむらいせき)から出土し、イギリスの大英博物館でも展示された巻貝形土器は後期のもので、宮古市にとって重要な資料になっています。
※縄文時代中期にかけて東北を中心に作られた深鉢形の土器。
発掘の現場では私も日常的に作業していて、今行っている現場では竪穴住居とものを保管するための土坑が2基出てきました。土坑に関しては平安時代かなっていう目途がついたんですけど、竪穴住居に関しては時期を特定できる遺物がなかなか出てこないのではっきりとは断定できなくて。ただ竪穴住居の特徴から古代だろうと想定しています。

――文化財を扱う上でいつも大事にしていることは?
上條:土器などの資料を取り扱うにあたっては、やっぱり持ち方に気を付けていますね。また発掘に関しては工期が決まっているので、ちゃんと間に合わせられるよう効率的に、かつ手際良く発掘することが求められます。でも私はあまり手際が良くないので、それで悩むことも結構ありました。期間内で完掘させるっていうのが絶対ですし、発掘するということはつまりそこに家を建てたい人がいるということなので迷惑もかけられませんし。効率良くっていうのが一番難しいですね。


出土した遺物の図面(実測図)の作成の様子。土器の場合、器の厚みや外側?内側の状態(模様や制作技法など)を記載していく。
――やはり大学で発掘作業をしていた時とは求められるものが違いますか?
上條:そうですね。私たちのように教育委員会とか市町村の場合は緊急発掘になるので、とにかく記録を残して最小の掘削で最大の効果を出すように言われるんですが、高畠町にある日向洞窟(ひなたどうくつ)遺跡※へ発掘に行っていた大学時代は、私たちがすっぽり埋まってしまうくらいの深さまでずっと同じ場所を掘り続けるという、あくまで研究のための発掘調査だったので、そこが全然違いますね。
※山形県東置賜郡高畠町にある、縄文時代早期~後期にかけて使用されていたとされる遺跡。


宮古市埋蔵文化財センターが併設されている崎山貝塚縄文の森ミュージアム。縄文文化を通じた環境教育や歴史教育に力を入れており、充実の展示内容。
――特に印象に残っているお仕事はありますか?
上條:2m以上手掘りした現場があって、道路をつくるための発掘だったんですけど、意外と浅いところで遺構が出てきたので「そこまで掘ったらもう終わりかな」と思っていたら、まだ遺物がたくさん出てきて「おかしいな」と。そこから深掘りという大きく深く掘る作業を行ったらもっと黒い土が出てきて、まだまだこれ続いてるぞって話になり、結果2mぐらいの掘削になりました。
夏の暑い時期だったので、時間だけでなく体力勝負なところもあって、それが今までで一番大変だったかなっていう印象ですね。本当にいろんな土器が出てきて、今作業員さんに接合作業をしてもらっています。土器の感じからして縄文時代の中期と後期、あと前期もちょっと入ってるかなと。そういった発掘の時、私は監督みたいな立場でいないといけないんですが、周りの人たちがどういう動きをしているのか、次に何の作業をしてもらうのがいいのかっていうのを一からちゃんと考える必要があるので、そこも効率の良さが求められる大変な部分ではありますね。

教科書には載っていない歴史を学ぶ面白さ
――歴史遺産学科に入ろうと思った理由は?
上條:もともと歴史が好きで、神社仏閣も大好きだったし、祖母の家の隣にある観音様にも興味があったし、祖母の家では縄文土器も拾えるみたいな。あとなぜか石器を親からもらって、実際に紙を切って遊んでいる幼少時代があったり。なので大学もそういう史学関係のところに行くことを考えていたんですけど、中でも芸工大は実際にフィールドワークに多く行けるところが魅力的だなと思いました。他の大学のオープンキャンパスにも行きましたけど、やっぱり芸工大が楽しくてAO入試(現?総合型選抜入試[専願体験型])で入りました。
あと地元が青森なので、同じ東北っていうのも大きかったですね。教科書の歴史よりもこういう地域に密着した歴史の方が好きでしたし、東北について勉強したかったというのもあって。ただ、気付いたら大学では民俗学ではなく考古学に突っ走っていました(笑)。
神社仏閣とかも本当に好きだったんですけど、やっぱり小さい頃の体験があったのと、あとAO入試の試験内容が「身近な歴史をまとめよう」というものだったので、青森県八戸市にある是川縄文館 でボランティア活動をしていたんですね。そこに縄文時代晩期のものが結構あったことも、考古の道に進みたいと思うきっかけになった気がします。
――今の仕事に活かされていると感じる学科の学びはありますか?
上條:やっぱりフィールドワークの経験が一番大きいですね。発掘に興味を持ってくれる地域の方って結構いらっしゃって、一緒にお話していると当時のフィールドワークととても似たものを感じますし、芸工大は地域の人たちと関わる機会が多かったので、それが今すごく役に立っています。地域を一番知っているのは、学芸員よりも地元の人だったりしますから。
あと大学時代のフィールドワークで特に印象に残っているのが、日向洞窟遺跡の中に這いつくばって入ったこと。平面図を取るために、スタッフという測量機材を使いながら洞窟がどこまで続いてるのか記録を取っていったんですけど、断面を取る人たちは上から紐を垂らしていく方法なのに対し、私ともう一人男の子は、クモの巣をかき分けながらだんだん狭くなっていく洞窟内を這いつくばりながら潜っていって。そういう経験は芸工大だからこそできたと思っています。座学では絶対に得られない経験でしたね。

――今後の目標などあれば教えてください
上條:もっともっと勉強して、できることをどんどん増やしていきたいです。行政にはまだまだ硬いところがあるので、そういったところに芸工大ならではの柔軟な発想を活かしつつ、いろんな発掘現場に行って、見たり触れたりしながら経験値を上げていきたいですね。
あと、先ほど宮古市周辺にはが多いとお話しましたが、これは岩手より南にある山形などでもよく見る土器の文化なんです。一方、宮古市は沿岸にあるため、動物の骨や角でつくられた釣り針などの骨角器(こっかくき)がたくさん出土していて、これは八戸などの北側から入って来た文化になります。つまり、この辺りというのは南と北の文化がぶつかるところで、両方の地域の特徴が見られることに最近とても面白さを感じているところです。

――それでは最後に受験生へメッセージをお願いします
上條:高校生の時、AO入試を機にボランティアでお世話になった八戸市立博物館の学芸員さんとは、今でも交流を続けています。そんなふうに、人とのつながりというのが将来いろんな形で活きてくるので、ぜひ大切にしてほしいですね。
それから歴史遺産学科を目指すなら、自分の地域の歴史に興味を持って調べてみるのもいいと思います。例えば疑問に思ったことはちょっと突っ込んで調べてみるとか、詳しそうな人に話を聞いてみるとか。そういうのってとても大事なんじゃないかなと。そもそも歴史が好きな人にはいろんなタイプがいて、私みたいに地域の歴史を学びたい人もいれば、高校の教科書の歴史をもっと深く知りたいという人もいるはず。でも芸工大で山形の歴史を学んでいると、教科書に載っている歴史はあくまで西の文化がメインであり、教科書は歴史の流れを把握するためにあるものだということが分かります。
芸工大の歴史遺産学科で学べるのは、そんな教科書の歴史から派生していった先にある地域の歴史。ですから、自分はどういう歴史が好きなのかを今のうちに見極められると、その後の進路がとても考えやすくなると思います。

? ? ?
現在は埋蔵文化財の管理や発掘などを担当している上條さんですが、入って1年目は学芸員としての経験も積んだそう。ミュージアム見学に来た小中学生に解説したり、岩手?山形?新潟の3県にだけ生息する『チョウセンアカシジミ』という蝶の産卵区域に行って卵の数を数えたり、またイベントや体験の企画を行ったり。そんな様々な経験を経て、専門分野である考古学の知識と経験をフルに活かしながら日々業務に向かっている上條さん。行政と大学とで発掘の目的に違いはあれど、フィールドワークで培った地域との関わりが、今も仕事する上で大きな支えになっているようです。
(撮影:布施果歩、取材:渡辺志織、入試課?須貝)
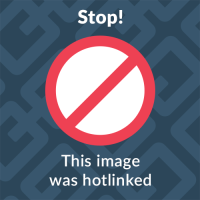
東北芸術工科大学 広報担当
TEL:023-627-2246(内線 2246)
E-mail:public@aga.tuad.ac.jp
RECOMMEND
-

2025.04.08|インタビュー
仙台から世界へ!多様なジャンルの人気作品制作に携わる充実の日々/株式会社MAPPA アニメーター?卒業生 佐藤碧
#卒業生#映像 -
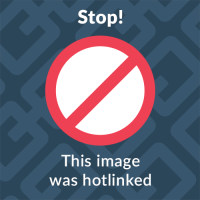
2024.04.08|インタビュー
型にはまらない設計の仕事と、思っていたよりやわらかい建築の世界/株式会社スターパイロッツ?卒業生 太田晴子
#卒業生#建築 -
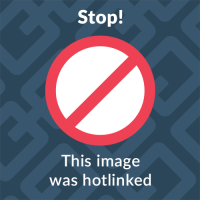
2022.03.10|インタビュー
目に映るものすべて、アニメを描く引き出しになる /Production I.G(プロダクション?アイジー)?卒業生 量山祐衣
#卒業生#映像




