
美術科洋画コースを経て、大学院芸術文化専攻洋画領域を修了した浅野友理子(あさの?ゆりこ)さん。近年は『VOCA展』や『東山魁夷記念 日経日本画大賞』などでの受賞、入選が続いており、新進気鋭のアーティストとして注目を集めています。2024年には学生の時から憧れていたという『国際芸術センター青森』でのアーティスト?イン?レジデンスに参加。国内外のアーティストたちと共に約1ヶ月半滞在しながら作品制作に取り組みました。
そんな浅野さんの仙台市内のアトリエを訪ね、普段の作家活動や大学時代に得た学びについてお話を伺いました。
? ? ?
地域に伝わる知恵と出会う
――はじめに現在の浅野さんのお仕事内容を教えてください
浅野:メインはアーティストとしての活動ですが、仙台市にある文化施設で受付業務のアルバイトもしています。あとは普段の制作と少し似た感じの仕事を受けることもあって、イラストを描いたり、自分が取材をして制作するタイプなのでテキストも少し書いたりしています。それから以前は東北歴史博物館でも文化財系のアルバイトをしていました。

――大学院修了後は歴史遺産学科で副手※1をされていたそうですね
浅野:歴史遺産学科の授業には院生の時からよく行っていて、田口洋美(たぐち?ひろみ)先生※2のウサギ狩りとか北野博司(きたの?ひろし)※3先生の土器づくりとか、あとはテキスタイルコース(現?工芸デザイン学科)での紅花栽培のように、山形ならではの文化を体験できるような授業にも学科関係なく参加していました。もともとは海外の文化により興味があったんですけど、山形にいたら「なんか日本も面白いな」って思えてきて、芸工大の東北文化研究センターのリサーチにも協力させてもらったりして。
ちょうどその副手をしていた頃に、宮城県塩竃市にある『塩竈市杉村惇美術館』や福島県猪苗代町にある『はじまりの美術館』で展示の機会をいただいて、植物とか食文化とか土地のことをリサーチして作品を制作するというものだったんですけど、そのあたりから自分に求められているものと自分の興味のあることの中身が一致してきた感じがありますね。

※1 教員を補佐するスタッフのこと。講義の準備やサポート、学生の指導補助など行う。
※2 考古学者。文化財保存修復研究センター長。2023年度まで歴史遺産学科で教鞭を執る。
※3 民俗学者。日本のマタギ文化や狩猟文化研究の第一人者。2022年度まで歴史遺産学科で教鞭を執る。
――今のお話にもあったように、普段は植物や食文化をテーマに絵を描かれているのでしょうか?
浅野:そうですね。植物を絵の中に描くことが多いんですけど、いろんな土地を回って、その土地の植物の利用方法とか食文化について直接教わったり、受け継がれてきたことを聞いたりしながら、それを絵の中に落とし込んでいます。基本的には自分が住んでいる東北を回ることが多いんですけど、場所にすごくこだわっているというよりは縁のある場所へ行く感じなので、場合によっては海外へ行くこともあります。

――そのテーマに行きついたきっかけは?
浅野:植物自体は学部生の時から描いていて、単純に“実”とか“種”とか存在それだけでいくつも受け継いでいけるみたいなスケールの大きさや、その造形にすごく魅力を感じていました。院生の時、大学の敷地内に落ちていた栃の実をたくさん拾ったことがあって、それを山間地域の郷土食である栃餅にするため、つくり方を教わりに鶴岡へ通ったんです。で、歴史遺産学科に土器のレプリカがいっぱいあったので、野焼きの授業の時にちゃっかり持って行って(笑)、煮こぼすみたいな感じで灰汁抜きして、実際に栃餅をつくって食べました。その一連の体験が、自分が今絵を描く時のスタイルになっていることもあって、栃の実は一番好きな植物ですね。
あとは大蔵村の人たちに取材をして灯籠絵を描く、肘折温泉での『ひじおりの灯』に参加したことも今のスタイルに大きくつながっています。

――取材の際は地元の方とどのようにお話されていますか?
浅野:結構、具体的なことを聞くようにしています。例えば小豆を使った料理について、畑の上で聞いたり台所で教わったりしながら、一見関係ないようなその人の家族のエピソードまでお話しいただいたり。あとは、おばあちゃんに教わったという薬草を家の中に保存している人の話とか。今も薬草として使い続けている人もいれば、もう記憶の中だけという人もいたりして、そういったお話を聞けることが個人的には制作する上ですごく重要で、描きたいなって気持ちが引き出されます。1対1でお話を聞く機会が多いのでその分コミュニケーション力が問われるんですけど、たまに心折れることもあります……(笑)。それでもやっぱり直接話を聞けること、その土地の人と出会えることは大きいですね。
――このお仕事の魅力と、アーティスト活動する上で大切にしていることを教えてください
浅野:毎回、知恵?知識が得られること、いろんな人に出会えること、その土地に行けること。それがいつも刺激になっていて本当にありがたいです。世界が広がっていく感じがしますし、作品ができあがって、その展示が始まる瞬間にも喜びを感じます。ずっと絵を描いていると同じような作品になっていきがちなんですけど、それを常に更新できるように、そして前の絵を超えられるように、というところを今後も続けていきたいです。やっぱり好奇心がないと作品はつまらなくなるので、描く自分のことも絵を見てくれる人のことも飽きさせてはいけないなと思っています。
あらゆる素材に触れた経験を活かして
――在学中は洋画コースで学ばれていましたが、2024年の『第9回 東山魁夷記念 日経日本画大賞』で入選するなど、日本画の賞も受賞されているそうですね
浅野:確かに私の作品って日本画っぽいんですけど、絵の具の使い方を見るとやっぱり油絵出身の人の使い方だねと言われます。ちなみに絵を描く時は、最初に日本画の顔料である岩絵の具と膠(にかわ)を使って描いていって、最後の「ここぞ」という時に油絵の具を使って描き込んだり、画面の中でその質感の違いを活かすようにしています。

洋画コースでは、伝統的な技法の学びはもちろん、いろんな素材を自由に扱わせてもらえたので、その時の経験が今の作品に活きていると感じます。あと『100点ドローイング』という洋画コースの演習もとても良かったです。名前の通り100点を超える数の作品を描いていくんですけど、そこでも結構いろんな素材を使ったりしながら、自分の中にあるものを出し尽くすみたいな。その授業が印象に残ってますね。
でも学生の時はあんまり作品を完成させられなかったりとかして、卒業制作もイマイチで……。当時はどこで完成とするかを決断できなかったというか。でもとにかく絵を描き続けて場数を踏むことで、やっと絵を完成させられるようになりました。
――大学生活で思い出に残っていることはありますか?
浅野:芸工大の学食ですね(笑)。ランチの時間になると必ず行ってました。あと宮城に戻ってきた今すごく思うのが、山形には温泉があったのが大きかったなって。当時住んでいた家の裏に『八百坊』という温泉があって、そこによく通ってました。それから学部生の時は『MUSIC PROJECT(MP)』というダンスサークルにも入っていて、そっちにばっかりという時期もありました(笑)。すごく楽しかったです。今でも一番会うのって大学時代の友人なんですけど、変わらず横のつながりがあって、連絡も取り合っていて、美術の話もできるというのが私にとっては本当に大きいです。

――将来に向けて何か思い描いているものはありますか?
浅野:今まで、自分が興味のある場所へ行ってその出会いの中で制作するみたいなことを淡々と続けてきて、きっとこれからもそうしていくと思うんですけど、アーティストはもっと今の時代に応えていかなければいけないという思いもあって。私の出発点はその土地に受け継がれているものへの興味なので、やっぱりいろんな土地の消えそうなものを絵画で記録していくみたいなことはずっと続けていきたいですし、それが自分にできることなのかなって思っています。
また、最近になってアートの力みたいなものを感じ始めたというか、自分のやっていることは絵画じゃない方法の方が伝わるのかなと考えたときもあるんですね。でも、絵だからこそ伝えられるものがあるという実感がようやく出てきた気がして。あといろんなアーティストの方たちと出会う機会も増えてきて、それぞれの作品や考えを聞いているうちにすごく「アートって面白いな」と思うようになってきました。やっぱり人との出会いって重要だな、と。まずは今できることを続けつつ、今後はアジアとヨーロッパの境目あたりとか、ジョージアとか西アジアとか、果樹の起源やルーツになっているような場所にも行ってみたいです。

――最後に、芸工大を目指す受験生へアドバイスをお願いします
浅野:とにかくやりたいと思うことをやり続けてほしいですね。私も絵を描き続けることで画力が上がっていったし、明らかに変化していったので、とにかく描いたりつくったりしていてほしいなと。高校生の頃から絵を描くのはすごく好きだったけど、特に「こうしたい」みたいなのがあったわけでもなくて、むしろこの10年ぐらいのすべてに意味があったと感じています。
あと、最近になってすごく展示とかを観るようになりました。本当は学生の時にもっとたくさん観るべきだったと思うので、皆さんには今のうちからいろんなものを観ておいてほしいですね。それから「絵は好きだけど、あんまり画力に自信がない」という人がいたら、夏期講習に行ったり、もし美術部であれば先生に教わるとか、そういったことに取り組んでみるといいんじゃないかなと思います。

? ? ?
普段は大きいサイズの作品をハイペースで描くことが多いという浅野さん。「私の場合、自分がコントロールできなそうなサイズの絵にどんどん挑戦してみたくなるんですよね(笑)。でもそれは芸工大のアトリエが大きかったから、っていうのもあると思います。大きければいいということではありませんが、学生のうちからそういうサイズの絵に挑戦できる環境があったというのは貴重だと思います」。大学の施設や山形ならではの環境を大いに活かしながら、自身の絵のスタイルを確立していった浅野さん。これからの活躍がとても楽しみです。
(撮影:渡辺然、取材:渡辺志織、入試課?須貝)
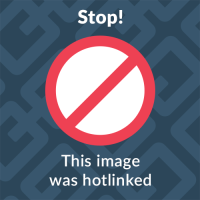
東北芸術工科大学 広報担当
TEL:023-627-2246(内線 2246)
E-mail:public@aga.tuad.ac.jp
RECOMMEND
-
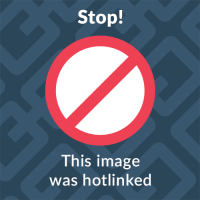
2023.03.03|インタビュー
人との関わりに喜びを感じ、社会の中でアートを生かす /社会福祉法人「愛泉会」?卒業生 髙力了生
#卒業生#総合美術 -

2025.04.25|インタビュー
自分の作品で、人と人との関係性や場を築いていける喜び/アーティスト?卒業生 大平由香理
#卒業生#日本画 -
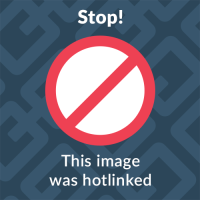
2023.03.03|インタビュー
自分が挑戦してみたい展示の企画を、一から考え作っていける面白さ/花巻市博物館?卒業生 髙橋静歩
#卒業生#歴史遺産




